私が人生でワインと出会うきっかけになったものがある。それは「クラッシック音楽」だ。
大人になってからというもの、新しい曲に出会ったとき、久々に思い出の曲を聴くとき、いつしか「この曲に合うワインを飲みたい」という感情が心に浮かんでくるようになった。
感情を揺さぶれる体験をしたときや、「音」と「旋律」に込められた喜怒哀楽に気づいたとき、フィナーレの感動にいつもワインが寄り添ってくれる。
今では大好きなクラシック音楽と、その1曲を最も愉しむことのできる1本を探すことが私流の「ワインの愉しみ方」になった。「音楽」も「ワイン」も、まだまだ経験値は道半ば…ではあるが、年々その奥深さに取り込まれつつある。

私が「生涯の問い」として出会った曲と、記憶と記録に残している1本。それはクラシックファンなら必ず語りたくなる、「あの名曲」だ。映画「ベニスに死す」のテーマ曲としても有名なグスタフ・マーラーの交響曲第5番4楽章「アダージェット」。その甘美だかどこか切ない旋律は、マーラーが作曲家人生で書いた最初で最後の愛する妻へ宛てた「ラブレター」とも、生涯唯一の「愛の調べ」とも言われている。
その人生からマーラーの作品には「死」をテーマに書かれた曲が多い(10曲ある交響曲だけでも、そのうち少なくとも8曲はそうだと思う)が、彼は第5番に「愛の楽章」を挿し込んでいる。曲全体の構成を大きく変えてでも組込みたかったようだ。

私がこの曲に出会ったのは、高校3年生の夏。年に1度しかない、吹奏楽コンクールの自由曲に選ばれたのがきっかけだった。高校生活の最後となる大会、歴代が連続出場している全国大会を私たちの代で途切れさせることはできない。さらに歴代のなし得なかった全国大会の金賞もねらいたい、そんな中で選曲された1曲だった。
当時はまだ「恋」しか知らない高校生。マーラーがこの曲の旋律を通して伝えている「生涯唯一の愛」を考えたこともなく…。私はただ目先の結果に追われるように、がむしゃらにマーラーの譜面と旋律と向き合った。10月の末に行われる全国大会までずっと。

私の担当は「ハープ」。曲の冒頭から静かに並ぶ音型を担っている。
少し専門的な話にはなるが、出だしのハープは「ド」と「ラ」の2つの音を分散和音。
「ド」と「ラ」は、「ファラド」という3和音から主音「ファ」を抜いた音。
大事な主音を入れないことで、調性感が曖昧となり、すこしミステリアスな響きが生まれている。
「この旋律で、絶望の果てにつかんだ愛の世界を表現しているんだ」
ただ譜面に並ぶ音符たちが愛に満ちた旋律だけでなく、どこかはかなく苦しみもだえる愛を垣間見せる、そんな旋律に感じられる。当時の私はそう感じた。いや、今思い返せばその程度の解釈だったといえよう。当時の人生観と、用意された時間の中では、そのくらいしか答えを出せなかったのだ。
ただ、高校3年生の私は、感じたままの想いを「ハープ」を使って表現した。
そして、なにか心の片隅に残った問いをこの曲に置いてきたまま、何処かクラシック音楽に取りつかれたように、大学を卒業するまでハープを弾き続けた。

その答えに少し近づくヒントを貰えた気がしたのは、社会人になってから。ワインにたずさわる仕事のなかで出会った1本がきっかけ。それは「フランソワ・ヴィラール」という人が造った白ワインだった。

使われるのは「ヴィオニエ」という名のブドウ。華やかかつ繊細な味わいが、綺麗なドレスを纏った貴婦人のようなイメージを彷彿させる。フランソワは、そのヴィオニエの頂点といわれる白ワイン『コンドリュー』の銘醸家だ。彼は幾人かの「重鎮」が存在するコンドリューの中で、実力派の一人に数えられる。ワイナリーの歴史は彼一代の手によるものだそうだ。
彼はなぜ、わずか一代で銘醸生産者と言われるほどのワインを造り上げることができたのか。彼をそこまで奮い立たせたワインとは、情熱とはなんなのだろうか。その答えは、私のあのハープの旋律につながるものだった。

フランソワは言う。
「私たちが大事にしていることは、土とブドウがワインを通して自らを表現できるようにしてあげることです」と。
ブドウや土という自然と向き合い、創り、そして自分とテロワールを表現し投影してワインを造る。これは音符や旋律と向き合って音を創り、自分と当時の感情を表現して投影する音楽と重なってくる…。
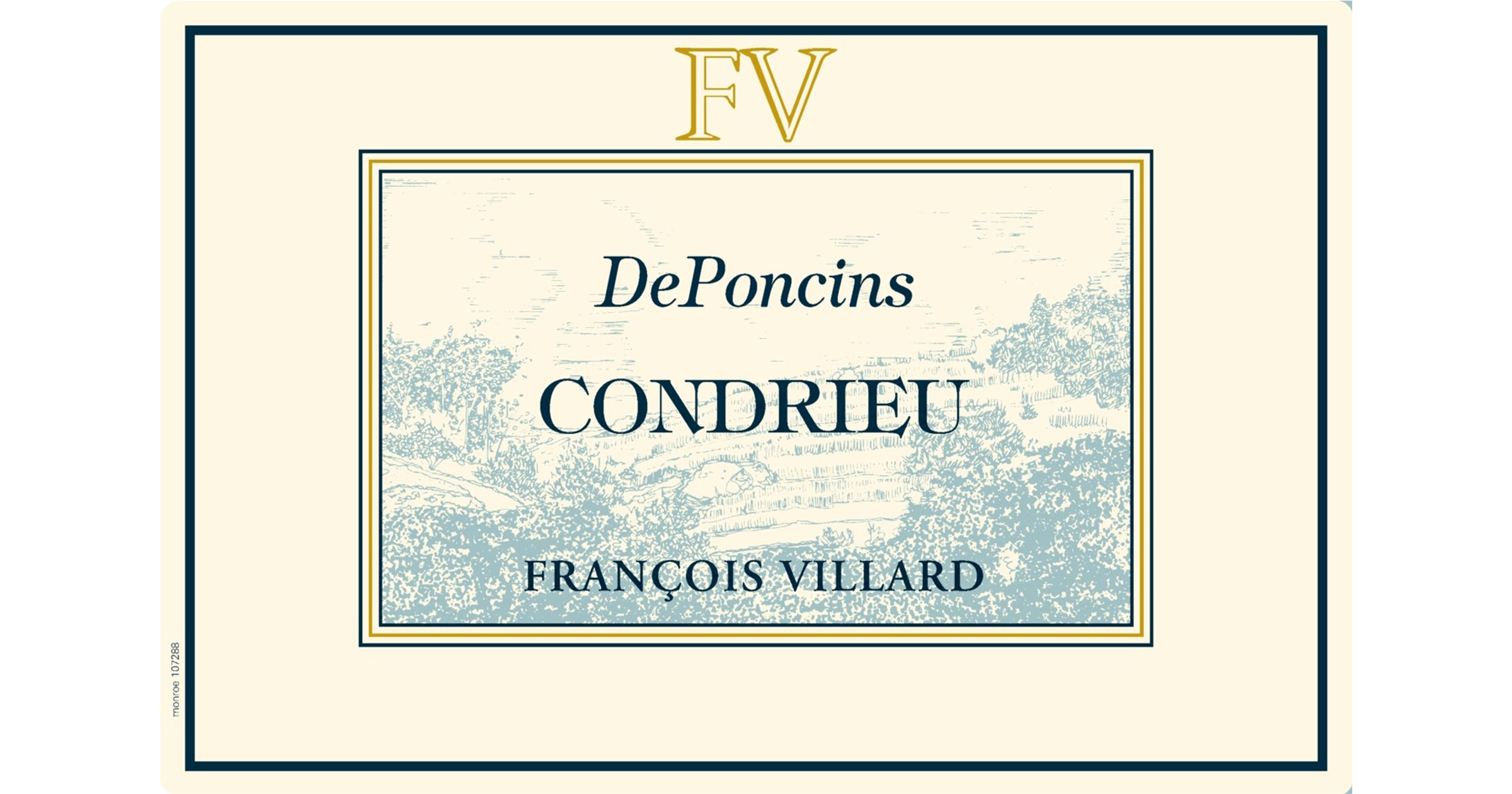
このワインを初めて口に含んだとき、高い集中力の中にある薫り高さと果実味、そして時間とともに口と記憶に刻まれていくどこか儚い(はかない)酸を感じた。重厚で古典的なコンドリューと一線を画し、フランソワ・ヴィラールのコンドリューはアルコール感が控えめでエレガント。かつテロワールの味わいを忠実に再現している。
たった一人「生涯の愛」を伝えようという情熱が創ったマーラーの音楽と、たった一代「自分自身の情熱」を表現したフランソワ・ヴィラールの造るワイン、図らずともその一曲と一本にどこか通ずるものがあるのではないだろうか。そう感じたのだ。
このとき私は、心の片隅に残ったままの問いがふっと軽くなった気がした。
「音楽×ワイン」はなんてすばらしいマリアージュなのだろう、その世界に出会った瞬間でもあった。

作曲家が譜面と旋律で思いを伝えるように、生産者も情熱とブドウで、ワインを通して自らを表現している。
マーラーが絶望の果てにつかんだ愛の世界の旋律と、言葉にできないけれども味わいで表現したフランソワ・ヴィラールのワインとのマリアージュが私の中で体現された瞬間だ。
冒頭、絶望の中を静かに漂う旋律には、少し大きめのグラスに注いだ時から溢れ出す、高い集中力のある薫りが寄り添った。
ワインが空気と沢山触れ合った2、3日目の果実のあたたかさと余韻のはかない酸には、終盤の柔らかくシルクの様な肌触りの旋律が寄り添う。
旋律とワインは、ともに切ないまでに甘い耽美的な感情を私にもたらしてくれた。



