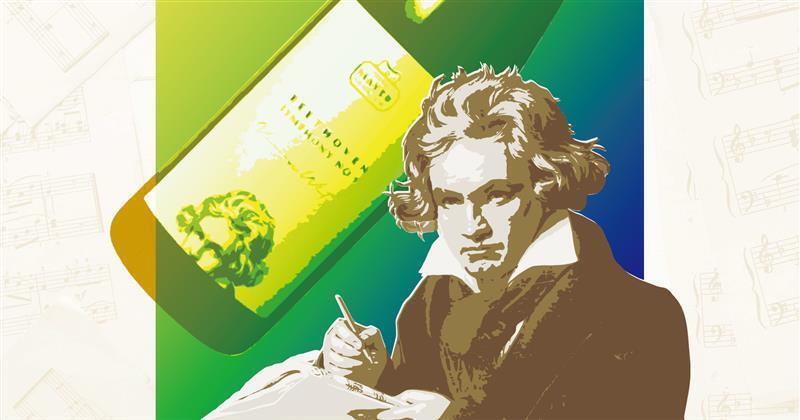『第九』
クラシック音楽を聴かない人でも、この曲名は聞いたことがあるのでは?
それほど日本人になじみ深く、年末になれば必ず耳にするであろう1曲だ。私がこのコラムを書くきっかけになったのは1本のワインである。
オーストリアの銘産であるグリューナー・ヴェルトリーナ種の白ワインで、ウィーンにある1683年設立の歴史的なワイナリーが造っている。敷地内にはベートーヴェンが住んでいて、第九を作曲した家屋「ベートーヴェンハウス」が残る。
ワイナリー『ヴァイングート・マイヤー・アム・プァールプラッツ』

奏者・指揮者で曲の印象を大きく変えるのが「クラシック」というものだが、このワイナリーを指揮者に例えるなら現代曲を得意とした近代の指揮者。テンポと抑揚を割とドライに仕上げるタクトのように思う。
ワインを開けた瞬間の、緊張感あるピリリとしたガス(微かな炭酸)は、どこか冒頭のティンパニの旋律を彷彿させ、この1本からどのような物語が始まるのかという期待を想起させる。『第九』は1時間を超える大曲だが、フィナーレまで待機する時間とこのワインの味わいのドラマには共通するものを感じる。
造り手が葡萄を栽培し、醸造して、熟成された期間に思いを馳せると、ワインがグラスに注がれ本来のポテンシャルを発揮した時の感動はひとしおである。

『第九』のことを説明するにはいまさら感があるが、この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(以下ベートーヴェン)が1824年に作曲した独唱と合唱を伴う交響曲である。楽譜が出版される毎に振られたベートーヴェンの作品番号は125番。最後の作品番号は138番(レオノーレ序曲第一番)だから晩年に作曲された曲だ。
初演(初めて演奏披露)されたのはウィーンで、1824年5月7日。
当時、54歳だったベートーヴェンは難聴が進み、この曲はほぼ耳が聞こえない中指揮したといわれる。
彼は交響曲第10番のスケッチを残して世を去った。完成させた交響曲の中ではベートーヴェンが生涯最後に書きあげた。
難聴に悩まされ、その上孤独で貧乏な最後だったベートーヴェンが、人間の生きる戦いを歓喜表現した、人類史上シンフォニー(交響曲)の最高傑作と呼び声高い。
私は中学校から大学までの10年間を吹奏楽に捧げた。音楽を続けていた中で「圧倒的に一番多く演奏したのはこの曲」と断言できる。
年末になれば誰もがよく耳にするであろう、あの有名な「喜びの歌」のメロディ(主題)に曲の冒頭からたどり着くまでのちょっとした小話を演奏家目線からさせていただきたい。

まずは、私なりの第九の解釈を。
第1楽章、専門的な話をすると、冒頭、ラとミの音(完全5度と呼ばれる明るくも暗くもない響きをホルンという楽器に乗せて、遠くの方からわずかに聞こえる演奏をしている。
調性がはっきりと判断できないようにぼやかしている。そんな不思議で暗闇の中から一気に、どこか最終楽章を彷彿されつつもドラマティックな旋律は、ベートーヴェンの不屈の意志だけではなく、強い問題提起を感じるのだ。
第2楽章、第1楽章を受け継ぐようなニ短調の主和音の降下がティンパニのインパクトに反映、現実に戻されるような感覚をもたせながら、終始軽快でテンポも良く、少し箸休めになるような時間が流れる。
第3楽章、個人的に一番好きな楽章。神秘さに満ちた安らかに進む緩徐楽章。その旋律は、優しさや悲哀を的確に表現したように感じる。
第4楽章、言わずと知れた「歓喜の歌」
第1楽章で感じた強い問題提起の答えがみつかる楽章でもある。各楽章を彷彿させる旋律は、各楽章の音楽に難色を示した後、人類の平和と友愛の理念を訴える歌詞と共に、壮大な歓喜の歌が放たれる。
第4楽章を聞き終えた後に、もう一度第1楽章を聞いてみるのもいいだろう。各楽章や最終楽章の片鱗が垣間見えるメロディーや旋律が随所にあることに気づくからだ。

年末に演奏される、聞きなじみがあるのは「第九」の第4楽章「歓喜の歌」。
この「歓喜の歌」は約70分に及ぶ全曲の最終部分で、ほんの一部にすぎない。
クラシック音楽になじみのない方にとって1時間を超える曲は、きっと良い睡眠導入剤になるだろう。かくいう演奏側の私も、「休符を数える能力」で、合奏練習時に睡魔に耐える能力を培ってきた。
私が担当していたパートは「打楽器」。この曲のティンパニを除く打楽器群は、「トライアングル」「シンバル」「バスドラム(大太鼓)」で構成されている。これら3つの出番は第4楽章のみ。約70分の曲の演奏が始まってから50分程度経ったころだ。
しかもラスト20分間、一番の盛り上がりを見せるフィナーレ中で叩いているわけではなく、そこでもなお休符(休み)がメインだ。

次に『第九』を聴く時には、是非この打楽器の出番に注目してみてほしい。そこには合奏練習時に度重なる眠気に打ち勝ってきた打楽器担当者のアツい一発一発が鳴り響いているはずだ。
クラシックには、多数出番が1回しかない楽器のある曲などたくさんあるが…。その話もまたいつか…。とにかく変わりダネの楽しみ方のひとつである。
『第九』の小話

海外で『歓喜の歌』はベートーヴェンを象徴する1曲であるのに対し、なぜ日本では「年末=第九」の構図が生まれたのか。
所説あるが、日本で初めて「第九」のコンサートを行ったのは、戦後間もない1947年のこと。新交響楽団(現在のNHK交響楽団)が、12月にコンサートを開催し絶賛されたことが、年末に「第九」を演奏する習慣へと受け継がれていく契機となった。ここに2つの説が生まれる。
一つ目は、合唱が新年にむけての臨時収入を得るアルバイトのひとつとして人気があり、年末になるとオーケストラのためにこの合唱付きの「第九」を歌う人が殺到したそう。まだ混乱期の真っ只中だった当時、ドラマティックな「歓喜の歌」を聴いて元気をもらい、新年への活力とする人も多かったとか。これが定番につながったというのが一つめの説。

もう1つは、オーケストラの「書き入れ時」が定着した、という説。第二次世界大戦後の混乱期に、NHK交響楽団の前身・日本交響楽団の第九公演が大当たりしたこと、それに加えて、アマチュア合唱団の活動が各地で盛んになり、合唱団の家族や知人がチケットを購入するなど、毎回収益が安定していること。そうした興行面でのメリットがあったため、というのが2つめの説である。

海外では、年末だからといって決まった楽曲を演奏する国は少ない。
世界的には「第九」はどちらかというと祝典や特別行事の際に演奏されることが多い曲。「歓喜の歌」だからだ。
ワインも音楽も突き詰めると様々な一面が見えるように、今回の「第九」という有名な一曲でもまだまだ知らない一面や隠された秘話がある。
是非このベートーヴェンラベルを味わいながら、「このワインが持つ物語」や「第九の成り立ち」に思いを馳せてみてはいかがだろうか。きっとワインやクラシックの奥深さと楽しさを感じていだけることだと思う。